■子どもが不登校になり絶望的な気持ちになった
―息子さんが小学1年生で不登校になった際の思いは
めいめい:ひと言で言えば、絶望です。私は、子どもに何かを禁止したりしない主義なんですが、小学校1年生の7月に学校に行けなくなった時には、自分の育て方が悪かったと思ったのです。自由にやらせすぎて勝手な人間になってしまったと思った。学校のルールに従えないから、行けなくなったと思い込んだのです。
それで、息子の将来をすべてぶち壊したのは私だと思ってしまいました。息子がこのまま家にいたり、何もできないで生きていくしかないならば、私も死ぬし、息子も生きていることは無駄なのではないかと思ってしまいました。
―育児史上最大のミスで「母子分離不安」を引き起こしたとか
めいめい:息子はある朝起きたら、ギャーっと泣いて「学校に行かない、わくわくプラザにも行かない」と叫んだのです。それでも、何とか学校に連れて行きましたが、日を追うごとに反発が強くなってきました。
ある時、学校の先生でもあるコーディネーターが、学校の昇降口で息子をガっと抑えて、「お母さん、仕事に行ってください!早く!」と言われたのです。それで息子に「じゃ、行ってくるね!」と言って走っていきました。すると息子が、「お母さん、行かないで!」と泣き出したのです。それでも、今までの私の甘やかしがいけなかったのだと思い、心を鬼にして走り去って職場に向かいました。
そこから分離不安が始まったのです。「お母さんは、僕を見捨てて行ってしまうんだ」と息子が思ってしまった。それ以来、私の脇を片時も離れなくなってしまいました。そこで、それから2年間、母子登校をしていました。

不登校で親も子供も精神的に追い詰められる(写真はイメージです)
■無理に学校に行かせなくてもいい
―とはいえ、母子登校もやめた方がいいと
めいめい:母子登校をずっと続けても、学校に行けないようであれば、原因はほかにあると思うのです。長い母子登校はお勧めしません。親の方が病んでしまいます。よその元気な子どもたちを見るだけで「なんで、うちの子はこうなんだろう…」と思ってしまうのです。息子が元気に手を振ってくれればいいですが、そんなことはなく、暗い表情をしていたりします。
一方、私は「登校を目標にしなくてもいい」とずっと言っていました。「元気でいられればいい」と思っていたのです。だから、学校に行くと元気がどんどんなくなってしまうならば、もう学校に行かなくてもいいという判断をしました。それからは、「今日はどうするの、学校に行く?行かない?」という声掛けもしなくなりました。
―不登校の初期段階ではどういう対応がいいのでしょうか
めいめい:本人が学校に行きたくないと言う時、単なる愚痴なのか、そうでないのかは見ていればなんとなくわかります。暗い表情で押し問答をするくらいであれば、学校に行かせなくていいと思います。元気な子であれば、一日、二日休んだら、再び学校に行けます。さぼりで学校に行かない子はほとんどいないのでは。

子どもも学校に行きたくても行けないで悩んでいる(写真はイメージです)
―死んでしまいたいという思いからどう立ち直りましたか
めいめい:不登校が7月に始まって、すぐ夏休みに突入しました。すると私が40度の高熱を出して、めまいと吐き気と貧血で倒れてしまいました。原因は不明だったのですが、息子のことがストレスで、自律神経が狂ってしまったのだと思います。
そこで、楽しんで子育てをするという基本に立ち戻ろうと思いました。そこから、頭が切り替わりました。また心理関係の本も読み漁ったので、本にも救われたと思います。さらに、職場が引きこもりの若者支援の団体でもあったので、理解があったことも助かりました。
■「めいめいサロン」は経験に共感し前向きになれる場
―ところでオンラインコミュニティ「めいめいサロン」を開こうと思ったきっかけは
めいめい:不登校児の親同士が話す場がないなと思ったことと、私が10年ほど前に行った親の会は、悩みのどん底の方が多く、みんな泣いていて空気が重かったのです。だから、毒を吐くのも大事ですが、そうではない、最後はほんのちょっとでも前向きになれる親の会を開きたかったのです。それで、オンラインコミュニティを開くことにしました。
「めいめいサロン」では、掲示板があったり写真投稿や情報を共有することもできますし、トークルームでの話し合いもできます。メンバーは有料の会員制にしています。なぜかといえば、サロンをかき乱すような人が入ってこられないようにするためです。本当に必要な人に入ってきてほしい。そのために少しハードルを設けているわけです。

「めいめいサロン」では親同士が活発に情報交換もしている
―「めいめいサロン」のトークルームではどんなことが話されるのですか
めいめい:例えば、昼夜逆転している子どもが、朝起きないで夜活動しているなどですね。そういう話を聞いて、アドバイスするというよりは共感してくれるのです。昼夜逆転の経験はなかったけれど、こういう苦しい経験をしましたと語る人もいます。
また、不登校経験者と私の対談も定期的にしています。それも親が参考にして助かっているようです。「こうして再出発できた」、「どうして欲しかったか」、「これはやめて欲しかった」など、不登校当時の気持ちをお伺いします。
■どんな人に対しても否定しないことが大事
―子ども同士のオンライン座談会「こずーむ」もあるそうですね
めいめい:月に1回、顔出しはしないでみんなが集まって好きに話すのです。最初は世間話で雑談をしていました。そうしたら、あるときに「お題を決めてやりたい」と言い出した子がいて、「それはいい考えだからみんなで話してみたら」と言いました。
親御さんたちには、「『こずーむ』での人間関係には口を出さないでほしい。喧嘩があったり色々なことがもしかしたら起こるかもしれないけれど、それも経験の一つ。社会に出たら必ずあることですから」と言って、それを理解してくれる方だけ参加してもらっています。
―「あじさいサロン」も開催していますね
めいめい:川崎市でリアルに開催している不登校児の親の会です。主に中原市民館で2カ月に1回偶数月第1日曜日に開催しています。一歩明るくなれるリアルな場所が必要だと思って始めました。「あじさいサロン」でも自分の苦しい事、悩み事について話したりしています。

リアルな話し合いの場として「あじさいサロン」も開催
―サロンではどんなことを大事にしていますか
めいめい:否定しないことです。その方の考えやお子さんを否定しない。どんな対応をしている方でも、どんな考えをお持ちの方でも尊重して黙って聞くことですね。
―親の不安に寄り添ううえで、大事にしている言葉はありますか
めいめい:話をお聞きした時の第一声は「そうなんですね」ですね。その方の言葉をまずは受け止めることです。その後に、例えば昼夜逆転しているお子さんなら、「考えようによっては、社会に役立つ可能性を秘めていませんか」と発想の転換で前向きなお話をすることがあります。
■食事はコミュニケーションをとるチャンスの宝庫
―食事の在り方を見直すと親子関係も良くなるとか
めいめい:食事はコミュニケーションをとるチャンスの宝庫です。部屋から出てこない子どもの場合でも、簡単な手紙を添えて食事を出すことができます。顔を合わせるのであれば、好きなものを用意してあげるとか、「美味しいね」と言葉をかけるだけでもいいんです。
―子どもの生活リズムを整える上での食の果たす役割は
めいめい:この時間に来れば、楽しい食卓がある、面白いことがあるかもしれないと、子どもに思ってもらえるようにすることが大事です。要は、親が規則正しくしていればいいということです。

規則正しく「楽しい食卓」を用意することが大事(写真はイメージです)
―「不登校でも大丈夫」と思えるにはどういう経験がありましたか
めいめい:元不登校の大人を知っていたことです。私が息子のことを隠さなかったからかもしれません。そうすると、「実は私も…」という人たちが現れてきました。そういう人たちと知り合えたことが大きいですね。
後は不登校の子たちが見ているネット上の掲示板を私も見ていたからです。それを見ているとどの子も苦しんでいました。それで、学校に行かせなくてもいいなと思ったのです。
―今後の抱負を教えてください
めいめい:具体的な抱負はありませんが、今、楽しく過ごせることをやろうと思っています。自分が、毎日、日常の中で小さな喜びがある…それが続けばいいなと。もちろん、「めいめいサロン」にはどんどん参加していただきたいと思っています。
―読者へのメッセージをお願いします
めいめい:不登校は人生の終わりなんかじゃありません。道の途中です。だから、そんなに心配することもなければ、不安になることもありません。親が楽しめば、子どもも元気になります。そのためにも、親同士がつながることが大事です!
「めいめいサロン」ホームページ:https://yoor.jp/door/meymey0404






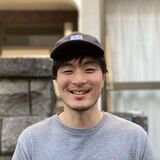











現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。