■人類の起源をたどる旅に出て会得した「生きる意味」
―大学時代に人類の起源をたどる旅に出たのはなぜですか
大塚:大学3年生の時ですが、もともと自分の関心が「人はなぜ生きるのか」ということでした。その答えを探しに日本中を回ったりもしたのですが、結局、よくわからなくて。それならば、人類の起源をたどったら、何かわかるのではないかと思ったのです。
アフリカ単一起源説だと、人類はアフリカの東側で二足歩行になった人たちがいて、そこから世界中に広がり、日本にもたどり着いたわけですが、それを逆ルートで辿ってみようと思い立ったのです。
―どういう順路でしたか
大塚:韓国→中国→チベット→ベトナム→ラオス→マレーシア→タイ→ミャンマー→インド→イラン→トルコ→ギリシャ→エジプト→スーダン→エチオピア→ケニア→タンザニア→香港です。ほぼずっとバスでの移動で、約160日かけて旅をしました。
―その旅の中で特に印象に残ったことは何ですか
大塚:エチオピアの草原で「牛飛びの儀式」を見たことです。牛を10頭並べて、その上を少年が走り切るとその少年は成人になるというイニシエーションです。
何十頭もいる牛の中から10頭選ぶのに何時間もかかるのです。並べた牛はじっとしておらず、どこかに行ってしまったりしますから。その隣では、女性たちが自分たちで作った綺麗な衣装をまとって歌と踊りをしていて、その脇で村長がお酒を飲んでいて、僕にも「一緒に飲もう」と誘ってくれました。
少年の「牛飛び」が成功するとお祭りが始まって、女性たちの踊りに男性たちも交じって踊りだしました。そのうちにだんだん暗くなり、夕日に照らされた草原に跳ねる人たちがいる…太古の昔から連綿と続く原風景を見て、生きる意味への気づきとして、創造力が大事なのではないかと思い至りました。
着飾っている衣装やアクセサリーは全て自分たちで作り、自分たちで創った歌や楽器、踊りがあって、自分たちで作ったお酒やごはんがあり…。なんといってもすごく楽しそうでした。
それで、食欲、性欲、睡眠欲という三大欲求を超える創造欲求というものがあると思ったのです。翻って、なんで僕はわざわざ危険をおかしてまで、この場にいるかと考えると、そういう創造性を見にきたかったからではないかと思ったのです。
それを冒険と捉えると、冒険欲求と創造欲求、誰かのクリエイティブを自分にインプットしアウトプットするという一連の循環が三大欲求を超えたところにあると思い、「冒険と創造」こそが人類の生きがいにつながっているのではないかという結論を得て帰国しました。その気づきを得たことが旅での一番深い体験でした。

エチオピアでの「牛飛びの儀式」
■待ち受けていた就職活動はあまりの「違和感」で放棄
―帰国後の日本は旅とのギャップが強烈だったそうですね
大塚:エチオピアの草原から2週間後ぐらいで帰ってきたのですが、旅の最後は異世界が凝縮されていたんです。エチオピアの後、ケニアのスラムやタンザニアのキリマンジャロに登って帰ってきたのですが、やはり日本との違いが強烈すぎて…。アフリカには生きる感動が詰まっていました。
その後日本に帰ってきたら、「なんでこんなにいっぱいモノがあふれていて、メシを食えているのに、こんなに生き生きとしていない人が多いんだろう」と違和感を覚えました。
海外に行った友達も周りにいたので、そういう友達と就職について話し合っているうちに、就職だけが道じゃないなという考えになってきました。そんな中である合同説明会の時に、話している内容が全く頭に入ってこなくなり、「よし、就職活動はやめよう!」と決めたんです。
■新卒フリーランスになって3年間で300本ものイベントを運営
―その後、新卒フリーランスになったそうですが、不安はなかったですか
大塚:不安はいっぱいでした。親も「大学を出たら、実家を出なさい」と言っていたので、実家を出たのですが、家賃も払えない状況でした。そこで賃料の安いシェアハウスに住まわせてもらい、着の身着のままなんとか暮らしていた状況でした。
―その時期はなにを考え、どう過ごしていましたか
大塚:ゲストハウスを作ることが大きな目標でした。そのためにどういうことができるかなと思いましたが、建物を借りるおカネはなかったので、ソフトゲストハウスという屋号で、建物は持たずに、場づくりの活動を始めました。その活動では、3年間で300本ほどのイベントを運営しました。
―どんなイベントをしていたのですか
大塚:一つ一つは小さいイベントが多く、多拠点居住の暮らし方などのイベントをゲストハウスやコワーキングスペースでやっていました。ただ、コロナ禍が起きて、それからは主にオンラインのイベントをやっていました。
その頃は地方関連のイベントが多かったですね。地方と首都圏をつないで、地方に行くきっかけを作るイベントなどです。また、場づくりに興味がある人たちが集まるオンラインコミュニティの立ち上げや運営などに携わったおかげで、ずいぶんつながりが広がりました。

新卒フリーランス時代のイベント風景
■住み開きシェアハウスとして住居の一部を街に開放する
―シェアハウスをやろうと思ったきっかけは
大塚:シェアハウスに住むことで生まれたつながりやサポートがあればこそ、こうやって生きてこれました。だから、恩返しではありませんが、いつかは絶対、自分もシェアハウスをやらないといけないなという義務感というか使命感が生まれてきたんです。後はシンプルにシェアハウスに住んでいて楽しかったし、その環境が自分を変えてくれたことも大きいと思います。
―「TACOHAUS」は住み開きシェアハウスですが住み開きとは
大塚:住み開きシェアハウスとは、住居の一部を街の人々に開放するものです。
「TACOHAUS」も道路に面しているので、近隣の人などが遊びに来やすいと思ったのです。地域の若い人たちのコミュニティができたらいいなと思っています。
―「TACOHAUS」はどんな間取りになっているのですか
大塚:1階は玄関とリビング、6畳の住み開きスペース、共用のトイレ、風呂、キッチンです。2階がドミトリー(カプセルホテルのようなもの)が4つと個室が2つ、ワーキングスペースが2席あります。

「TACOHAUS」のリビングでの焼肉パーティ
―どんな人が住んでいたり、訪れていますか
大塚:住んでいる人では、主に20代~30代前半で、結構活発な人が多いです。訪れてくれる人では、お子さんを連れて来てくれる近所の方や、同世代で近くに住んでいる一人暮らしの方、中原区役所
―共同生活をする上でのルールはありますか
大塚:ルールは作らないことにしています。これは僕がもともと住んでいたシェアハウスの教えみたいなものですが、ルールを一個作り始めると、数限りなくルールを作ることになるという学びを得ました。
―住み開きでのイベントで記憶に残っているものは何ですか
大塚:まずはDIYイベントですね。近所の人から昔からの友達までたくさんの人に改装を手伝ってもらって「TACOHAUS」は始まりました。みんな楽しんでDIYに手を貸してくれて、本当に感謝しています。
「フライドポテト展」も個人的に印象に残っていますね。チェーン店のフライドポテトを集めて、その中でどれが最強かを選んだのですが、次にはクラフトコーラ選手権を考えています。その後、ハンバーガーの選手権もやって、最後は、最強のハッピーセットを作りたいと思っています。
後は、「よなよなブックス」という本を読む企画で、この住み開きスペースに寄贈してもらった本を読むという時間で、後半、テーマを決めて話をしたりもします。また、定期的に梶さんという仙人のような方がお茶会を開いてくれたりしています。

「TACOHAUS」の住み開き部分で開催された「フライドポテト展」
―今後の抱負を教えてください
大塚:地域のハブと言われる「この地域に行くなら、最初にここに行くといいよ」という場所が日本各地に点在していますが、「TACOHAUS」がこのまちのそういう場所になったらいいなと思っています。
まちの人同士やまちの人と外の人がつながって、そのつながりから一つでも多くの面白い何かが生まれるような場所になっていくようになれば嬉しいなと思います。
―読者へのメッセージをお願いします
大塚:「TACOHAUS」は、住む以外の関わり方もできるシェアハウスなので、ぜひイベントなどで遊びに来てください!また、インスタグラムなどでイベント情報をチェックしてもらえたら嬉しいです!











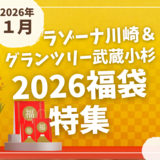





現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。