■副業としてシェアハウスの運営に乗り出す
―なんでも屋さんとご自身で言われていますが、どんなことをされていますか
小出:本業は大手IT企業のサラリーマンで20年近く研究職でした。今は新規事業開発を担当しています。副業の中で大きなウエイトを占めるのが不動産関係で、自分の資産管理会社があって、物件を持って家賃収入を得たり、リフォームして価値を上げて売って利益を得ています。
また、別の会社では、業務委託的に営業として物件売買をやっています。そこでは、全国の物件を見て、面白い物件を見つけて、その物件を買ってくれる人を探して、マッチングしたりしています。
それとは別に、自分にとって面白いことをしたいということでシェアハウスの運営をしています。その中の一つが、このギークハウス新丸子です。また、荻窪にも同様のシェアハウスを運営しています。また、一戸建てが西国分寺にあって、若者の挑戦のために一棟まるごと安価に貸しています。
さらにRooptDAO合同会社で業務執行社員という立場で、経営権を持って参加しています。この会社は、国内で法人格を持ち、DAO(自律分散型組織)を実践する新しい試みのための会社です。
―ところでギークハウスに関心を持ったきっかけは
小出:ギークハウスの草分けであるphaさんが、ギークハウスという名前をブランド化してくれて、だれでもやっていいよという形でやっておられました。このやり方は、オープンソースという考え方とすごく親和性が高くて、みんながやりたいことをやればいい、それに対して、何も権利を主張しない…そういうコミュニティづくりをしている感覚ですね。その考え方に前から注目をしていたのです。
一方、会社に入ってしばらくして、「この場にずっと居続けていいのかな」と不安を感じていました。研究職として作った技術がすぐに世の中で役に立つかといえば、なかなかそうはならない。技術を作ってから、それを製品にするまでにすごい壁があります。それならば、自分で研究して、仲間を募って自ら事業も立ち上げた方が面白いのでは、と思ったのです。

ギークハウス新丸子が入居するマンション
■大切にしている価値観は「自由・自治」
―ギークハウスを運営するうえで大切にしている価値観やルールは
小出:自由ですね。自治に任せるということです。そこは頑なに守り続けています。ぎちぎちに会社組織的に運営すると成り立ちません。住民それぞれの思いをちゃんと汲んで、コミュニティとしてどういうふうに文化を作っていくかという観点が大事だと思っています。
僕は管理人とかオーナーの立場になるので、どちらかと言えば、ルールを決めるという立場にあります。そこであえて「ルールは決めません。今いる人たちなかで、自分たちが一番心地よくなるルールをみんなで決めよう」と言ったのです。
―このギークハウスにはどういう方々がお住まいですか
小出:ジャンル的にはIT系の人たちですね。プログラミングをしている人、もしくはしたいと思っている人、webデザインやゲームデザインをしている人などです。ただ、IT系じゃなければ入居できないわけではありません。ITに興味を持っていてくれればOKです。
―住人が成長するための環境づくりで工夫されていることは
小出:イベントですね。後は、場所が大事だと思っていて、かなりの部分を共有スペースにしていて、入居者ができるだけ共有スペースで過ごすようにしています。ですから個室は作らないで、寝室は2段ベッドだけにして、完全に寝るだけの部屋にしています。
目的は、どれだけ人と接触してもらえるかということです。そこに成長のチャンスがあると思っていて、無意識的に人と接触できるような環境にしています。

広々とした共有スペース
―イベントとは具体的にはどういったものですか
小出:基本的に勉強会のようなものです。そのイベントも僕が主催するのではなくて、住民の誰かが主催しています。そうすれば、主催者もイベント開催のノウハウを身に着けることができますし、コミュニティをどうマネジメントするかの勉強にもなります。もちろん、その勉強会で、参加者は新たな知識を得ることもできます。

勉強会のイベントも和気あいあい
■「ごみ捨てマイニング制度」で暗号資産GMKを導入
―「ごみ捨てマイニング制度」というものを作られたとか
小出:ざっくりいえば、GMKというおカネを作っています。ビットコインのような暗号資産の一種ですね。その暗号資産でなにをしているかと言えば、シェアハウスの中の管理業務を楽しくできるようにする仕組みです。今はごみ捨てをみんなが自発的にやりたくなるような仕掛けをつくっています。ごみを捨てると暗号資産の一種であるGMKが報酬としてもらえるようになっているんです。
ですから、ごみを捨てれば捨てるほど、暗号資産が自分のところに入ってきます。その暗号資産を使える先も自分たちで決めています。たとえば、自分の持っているスキルをGMKと交換できるようにしました。自分の持っているスキルがいくらになるのかも、自由に決めてもらっています。
僕が提供しているのは、乾燥機を1回200円で回していいことにしていますが、それをGMKで払ってもいいよということにしました。

ビットコインのような暗号資産を発行(写真はイメージです)
■DAO的運営には課題も多いが可能性も大きい
―最初の立ち上げから14年が経ちましたが変化はありますか
小出:そもそもシェアハウスが特別なものではなくなったので、集客力がかなり下がりました。最初に立ち上げた2011年当時は、シェアハウスがあまりメジャーではなかったので、とても珍しがられました。かつ、単純にみんなで住むだけではなくて、テーマ特化型にしたので、だいぶ時代の先端をいっていました。ですから、ツイッター(X)につぶやけば、いくらでも人が集まってきました。
しかし、その後、だんだんシェアハウスも普通になってきて、特化型のシェアハウスもたくさんできてきたので、埋もれていきました。その段階でコロナ禍が起き、一緒の空間に人がいるということがあり得ない状況になりました。既存の住人で残ってくれる人はいましたが、新規で入居を希望する人がほとんどいなくなってしまいました。
―その危機をどう打開しましたか
小出:コロナ禍が起きる前には、手を広げていきたいと思っていました。それで、どんどん新しい物件を仕入れていたので、かなりの赤字をかぶってしまいました。そこで物件をどんどん手放して、ギークハウスはこの新丸子と荻窪に集中させました。それで、なんとか持ちこたえることができました。
―DAO的な運営を実現するうえでの課題や可能性は
小出:課題としては、なんだかんだおカネがかかることですね。最近のDAOはビットコインなどを取引するだけでものすごいおカネがかかります。ツールの費用だけではなくて、ベースにあるブロックチェーンのための費用も無視できなくなりました。
そのうえで、DAOとして、またコミュニティとして成り立たせられるかという運営スキルも必要になってきます。それがないと崩壊してしまいます。これも課題です。
可能性としては、自律的に人が集まってくる、かつ、そこの中で、自分は何をやったのかということを示すことができるので、新しい形のポートフォリオを組むことができることです。例えば、アーティストやデザイナーが「このサイトを作りました」という実績を個人として持って、それを見せることで仕事をもらったり、どこか就職したりすることができます。
―今後の抱負を教えてください
小出:一番やりたいのは本業とつなげることです。本業と副業というのは、公私混同ではありませんが、どんどん混ざっていくべきだと思っていて、いよいよそれができる時代が来たなと思っています。
―読者へのメッセージをお願いします
小出:ここに来たら住まなくてはいけないというわけではないので、勉強会などオープンに開催していて、FacebookやLINEのオープンチャットでお知らせしているので、そういう機会に、ぜひとも来てください!
そういう機会がなくても、何か興味があったら、気軽に来てほしいと思っています。色々とお話をさせていただいて、「それ、面白い!」と思ったら、ぜひ、一緒に何かやりましょう!ここは住む場所というよりも、何か新しいことを試せる場、自分が輝ける場所にしたいので、住んでいる人も住んでいない人もそういう場所として使ってほしいなと思います。






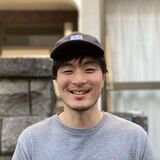











現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。