■若者から高齢者までスポーツでつなぐ
―「ふれあい無くして、街の発展なし」がキャッチフレーズですが、武蔵小杉周辺のように次から次へマンションが建って、単身者や高齢者などで孤立している方も増えています
原:私が市議になりたての平成23年頃は、タワーマンションが建ち始めた頃でした。そこで、タワーマンションの方と以前からお住まいの方との間で軋轢が出ないように、タワーマンション一帯のコミュニケーションをつなぐNPO法人武蔵小杉駅周辺エリアマネジメント(当時)の理事長と連携を図りながら活動をしていました。
また、地元の活動として、高齢者の方々のためにグランドゴルフやゲートボールなど色々なサークルの立ち上げに関わってまいりました。また、若い方々を対象としたソフトボール大会を毎年企画しています。ひと頃は24チームもあるほど人気でした。

子ども会のドッジボール大会に参加
■ダイヤル「189(いちはやく)」が整備され児童虐待を早期発見
―子育てで孤立してしまう人も増えています
原:昔は隣近所に子どもを預けることができましたが、今は、何かあったときに責任問題が起きてしまうので、なかなかそういうことはできなくなりました。そうしたご近所付き合いが希薄となり、悩みを抱え孤立した親が増え、結果的に子どもに手をあげてしまう親や育児放棄をしてしまう親が増えてきているのではないでしょうか。
―子どもの虐待に関して、平成24年に議員提案で、「子どもを虐待から守る条例」を可決しましたが、どういう取り組みをしていますか
原:平成23年に初当選して、この議員提案の条例のプロジェクトチームの一員となりました。当時、国で「児童虐待防止法」が成立し、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」が整備されました。
発信した電話の市内局番等から(携帯電話等からの発信はコールセンターを通じて)当該地域を特定し、管轄の児童相談所に電話を転送するシステムです。
虐待の見逃しはダメだということで、疑わしくはまずは見に行ってもらう…通報があったならば、児童相談所の職員が家庭に見に行って、様子を伺い、必要とあれば子どもを保護するということになりました。
虐待件数は年々増加傾向にあります。これは、虐待する家庭が増えたわけではなく、以前よりも虐待が表面化したからではないでしょうか。今までは、お子さんも言えなかった。親から受けている躾と虐待の区別がつかなかったので、ずっと明るみに出なかったわけです。
それを周りの大人たちが助けてあげよう、本人からも言ってもらおうということをどんどん進めたことによって、件数が増えたという一面がうかがえます。
■保育園の器が増えても人手が足りない
―一方で、保育園の人手不足、幼稚園の減少という問題が起きています
原:幼稚園は園児の減少が大きいですね。7年前では川崎市全体で23,000人程度の幼稚園児がいましたが2、3年前では15,000人程度まで減少しています。
共働き世帯が増えて、午後3時頃までしか預かってくれない幼稚園から、夜まで面倒を見てくれる保育園に子どもが流れています。
平成27年から待機児童ゼロの実現に向けて川崎市もどんどん保育園を整備したので、保育園の器はあるわけです。ただ、人手が足りないというのが現状です。地方では過疎化が進み保育士が余るといった状況を踏まえ、保育園協会などが地方から保育士を招くマッチングなどの取組みを行っています。
■「イクボス宣言」応援で働き方改革が前進
―平成28年に川崎市の「イクボス宣言」を応援する決議をされていますが、職場のボス(上司)が育休や介護を率先して進めているのでしょうか
原:働き方改革の一環として進めています。簡単に言うと上司は親の介護、部下は育児の必要性に迫られています。ですから、組織の中でも無駄な会議などを減らし、業務の効率化を図り、仕事と家庭の調和であるライフワークバランスを推進しています。
川崎市役所も率先して取り組んでいます。平成30年から「イクボスアワード」を実施し、優れたマネジメントや部下のワークライフバランスへの支援を実践する上司の取組みを表彰しており、働き方改革は間違いなく進んでいると思います。
我々も市議会での質問などを検討する際に、自分の都合でひとりの議員が市職員に待機してほしいと求めると、何人もの市職員が残業しなければならなくなります。
そこで、そういうことはなるべくやめて、市職員にもなるべく負担をかけないように対応していこうという趣旨が、決議の中に盛り込まれています。
われわれ議員も議員個々人のプライベートを尊重し、育児、介護、配偶者の出産補助などに関して、本会議等の欠席理由として認めて、議員のなり手不足の解消や女性の社会参画を促進する環境を整備しています。

国内初の「特別市」を実現できるか
■神奈川県から独立することで迅速な行政を実現
―中原区をどんな街にしたいですか。特別市を目指しているそうですが
原:みんなが顔と名前を知っている街にしたいですね。まず、すれ違う人たちが挨拶しあうといった当たり前のことが今は当たり前ではなくなってきているので、そういう小さなことからやっていかなければならないと思います。
特別市というのは、神奈川県から独立しようという構想です。川崎市は政令市ですから、権限的には神奈川県に頼ることは99%ありません。
しかし、税制面で市・県民税ひとつとってみても、たとえば1万円県民税をいただいた場合、そのなかで川崎市のためにいくら使っているのかと言えば、20%程度しか使っていません。
つまり、7,000円以上は県が調整し、川崎市以外で使います。ただ、神奈川県内の観光などの振興も必要ですから、100%川崎市のために使えとは言いません。
せめて7対3か、6対4ぐらい川崎市に使ってもらいたいと思います。川崎市、横浜市、相模原市の3政令市でおよそ600万人の人口となり、神奈川県の3分の2の人口規模を持っています。神奈川県はその財源を頼りにしていることになります。
例えば、神奈川県の防災ヘリは、川崎市の2機と横浜市の2機だけで県は持っていません。そのランニングコストが年間2億円かかります。神奈川県は川崎市に対して防災ヘリのために6~7千万円程度の負担をしていますが、実際の経費としては足りていないのが実情です。
さらに障がい者や幼稚園への県の補助金は一般の市へは2分の1支出されますが、川崎市を含む政令市には3分の1しか補助されません。政令市であるということでの不公平もあります。
一番痛感したのが、コロナ禍におけるワクチン接種の対応です。国が供給して、都道府県が分配、各市町村が接種という三位一体の動きの中で、第1回目の接種の時に、国は県に対してワクチンを送っていても、県がどう分配したらよいのかわからなかった。
単純に言えば、人口比率で分ければいいと思いますが、待てど暮らせどワクチンが来なかった。川崎市が特別市になれば、ワクチンは国から直接川崎市に供給されるようになります。それ一つとっても、ワンクッションなくなるだけで、スムーズに事が運びます。
災害支援もそうです。市町村は自衛隊派遣要請ができません。派遣要請は都道府県知事の権限だからです。この対応も特別市になれば国に直接要請できるようになります。県を挟まずに国と直接交渉できれば、スピーディな救援が可能になり、物資や医薬品も直接届けられるわけです。
確かに特別市になっても、平時ではそのメリットをなかなか感じづらいかもしれませんが、コロナ禍や災害といった非常時を考えた場合、国と直接交渉できることによる迅速な対応をイメージしていただけるかと思います。
とはいえ、まだ、特別市に対して、市民の皆さんに周知が進んでおらず、神奈川県との調整も引き続き必要ですので、道半ばというところです。


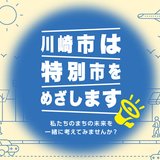















現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。