■人事本部に配属されて経営者と同じ視線で組織を俯瞰する
―大学を卒業した後にいったん音楽業界に入られましたね
大西:もともと両親が音楽家なんです。弦楽器が専門で、母は琴の先生で父はギターをはじめ色々な弦楽器を演奏することができました。父は早くに亡くなったのですが、祖父が墨絵をやっていたりして、サラリーマンがほとんどいないような家系なんです。
ただ、自分には演者としての才能というのがないなというのを早くから気づきました。そこでレコード会社とかラジオ局やテレビ局といったメディアで、スポットライトが当たる人たちの支援をしていくことができないかなと思って音楽業界を選びました。
―転職したDeNAはIT業界で、音楽業界とはかなり違いますが、それはどうしてですか
大西:最初の会社が株式会社有線放送ブロードネットワークス(現U-NEXT
HOLDINGS)で、営業として入社しましたが、どうしても音楽をやりたいと思って、音楽制作の部署に異動させてもらったのです。しかしそこで壁にぶつかりまくって…。新しい企画提案がなかなか通らないということが続き、これは自分自身のビジネスの総合力が非常に低いからだと思い、業界を変えて総合力を身に着けるために、IT業界を選びました。
―株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)に入社されて人事本部に配属されましたね
大西:入社して4年後くらいに人事本部に配属されました。もともと入社直後は、モバイルサービスの開発部門に配属されたんですが、ITの基礎知識もほとんどない自分は、どうしたら周りの同僚のレベルに一気に追いつけるだろうかと考えました。そこで周囲の優秀な社員やイキイキしている社員に声をかけ、自分のわからないことを質問攻めにしました。
その時に様々な部署の人と話ができて、たくさんの社員を知っている状態に早くからスタートできました。そうやって全社的にもある程度、顔と名前を知られて、開発現場やサービスを知っている状況になっていきました。それで、当時の役員から人事に異動しないかという話をいただきました。
一番よかったなと思うのは、経営者と同じ目線、同じ視座で会社や市場をみることができ、経営者と対等に議論することができたことです。だから、この事業戦略を成功させるためには、どういう組織であるべきかと、人事戦略を提案もできます。すると事業の責任者がいるので、その事業責任者とパートナーになって人事戦略を作っていったりとか、それに基づいた採用計画策定、採用イベント開催、さらには社内の人員配置も担当していました。
―その経験を「かわさきFM」の代表取締役に出向してどう活かしているのでしょうか
大西:広い目線でいうと、川崎市全体が組織だったりするわけです。様々な川崎市の地域の方や企業の経営者の方を知って、あの人とこの人が一緒になると面白い化学反応が起きるかなと、人のつなぎ役になったり、我々かわさきFMが地域のハブになったりということをどんどんやっているのは、多少、人事の感覚があるのかもしれません。
■「シビックプライド」を醸成するための2つの試み
―着任後すぐに、バスケの川崎ブレイブサンダースの試合の実況中継を始めましたね
大西:かわさきFMは開局から約30年の歴史があるなかで、早い段階から川崎フロンターレのホーム試合は毎回、実況中継をしていて、技術的にも内部の制作的なノウハウもたまっていました。それならば、ほかのスポーツに転用できないのかという話をして、男子バスケットボールのBリーグ「川崎ブレイブサンダース」の試合の実況中継を始めることにしました。

就任後すぐに着手した川崎ブレイブサンダースの試合の実況中継
―ところで「シビックプライド」(市民としての誇りや愛着)を醸成したいとか
大西:具体化した番組が2つあります。ひとつは、子どもが参加する番組の企画です。例えば、子どもがラジオ局でおじいちゃん、おばあちゃんなど遠方に住む親せきに手紙を読むという企画をやりました。また、キッズのラジオDJ体験として、子どもにDJブースに入ってもらい、こちらで用意した原稿を読んでもらったり、自分たちで原稿を書いて、完全に1本の番組を作ってもらい生放送でそれを流すという番組もあります。

子どもがDJを体験できる番組も制作
もうひとつは、高校生バンド王という高校生のバンドフェスティバルを立ち上げました。高校時代にこういうイベントに出て、みんなで泣いて笑ったよねという体験をしてもらうのです。そうすれば、その子たちが後々、川崎市で子供を育てようという気持ちになってくれるのではないかと思ったのです。
高校生バンド王は川崎ルフロンの野外ステージで開催され、かなり人も集まります。ラジオではライブの中継もしますし、事前に舞台に立つ7バンドにスタジオに来てもらい自分たちのバンドのPRと意気込みを話してもらいます。
また、優勝バンドには、ラジオの冠番組をプレゼントしています。そこは大手メディアではなかなかできないことで、地域のメディアがこういう体験をどんどん提供して、開かれたラジオ局でいれば、今後の川崎の街を作っていく一助になるのではないかと思っています。それがいわゆるシビックプライドの醸成に貢献したいことです。

野外ステージで開催される「高校生バンド王」フェスティバル
■認知度を上げることが大きなテーマ
―ローカルメディアの面白さと苦労はなんでしょうか
大西:面白さは地域の特性が全面に出ることですね。同じ関東でも、全然状況が違いますし、推しポイントも違いますし、それぞれの特色を存分に出していくことが大事だと思います。そういう意味では地域のスポーツというのは、本当にカラーがしっかり出ますから、そこがいいなと思います。
また、顔が見える関係が築きやすい。私も色々な会合に出たり地域の団体に入っていると、番組の出演者の方にいたるところでお会いして、色々なご意見を伺えます。とても近い距離で、「その意見いいな、取り入れよう」とか、「そんな問題があるのか。どうしたら解決に動けるのだろう」など情報共有ができたり、課題解決の糸口になっています。

地域で活躍する人をゲストに迎え、顔が見える関係を築く番組「コスギ スイッチON!」
苦労でいえば、第3セクターなので、認知度が大きなテーマになっています。ラジオ離れみたいなことは色々な記事で出ていますが、ラジオとテレビというのは、今の忙しい社会人には、なかなかリアルタイムで聴くということの難しさが出てきていると思っています。
ですから、後から聴けるということの整備が非常に大事だなと思います。一部、試験的にアーカイブでの聞き逃し配信とか、YouTubeにコンテンツをあげるなど後で視聴できるシステムの導入を始めています。これを今年度はしっかりと基盤を作っていこうと思っています。
■防災時に対応するためにAIのシステムを導入
―「かわさきFM」は第3セクターですが、その特徴は何でしょうか
大西:川崎市の防災情報の放送や、地域の防災力を上げるということの一端を担っているので、その責務というのは非常に大きいと思っています。災害が起きた時には、川崎市から直接連絡が来たり情報が流れてくるので、それをこちらが常に受けて放送できる体制を組んでいないといけません。それは土日でも深夜でも早朝でも変わらずということなので、その体制整備には力を入れています。
―放送も24時間体制ですね
大西:深夜と日曜日は社員を休ませていますが、その間に災害が起きた場合に対応するためにAIのシステムを導入しました。総務省に「Lアラート」という災害情報が集まっているデータベースがあって、そのデータを基にAIが原稿を書き起こし、読むことができるようにしています。また、それを自動的に本放送の中にカットインさせるという仕組みを整備しました。
まずは一次的にAIが自動的に動いて放送を流すことになっています。また、社員が放送局にいなくても、パソコンがあれば自宅からリモートで操作できます。ですから、AIが書き起こしたものをちょっと書き直すことや続報が出た時にそれを原稿としてAIにセットして読ませて本放送にカットインさせることができます。その間に、放送局の態勢を整えて、アナウンサーを探したり、スタッフを集めたりします。
―今後の抱負を教えてください
大西:我々が認知度を拡大していくためにも、開かれたラジオ局ということで、みなさんに知っていただくような機会を作りたいということと、放送をYouTubeと同期させて、ライブ配信ができるような仕組みを整えました。今後はラジオで聴く方は聴いていただきながら、映像で見たいときはYouTubeで見られて、そのままアーカイブで残っていくような聴き方の整備をしっかりやっていきたいと思っています。
―読者へのメッセージをお願いします
大西:かわさきFMにぜひ来てください。こんなネタがありますという方は、それをPRしにご出演いただいて体験してください。出演して楽しい!と感じていただいたり、何ができるのかを分かっていただけると、認知度の向上にもつながります。みなさん、ぜひ来て出演してください!









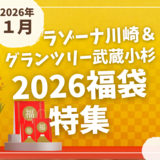
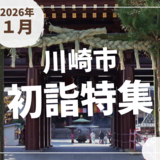
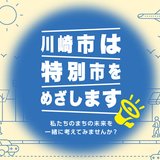





現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。