■問題意識を持った教育委員の経験
―選挙に出馬したきっかけは何ですか
高橋:2018年から川崎市の教育委員として、川崎市全体の子どもの教育、市民の皆さんの社会教育などを考える機会をいただきました。さらに、月給272,000円ものお給料もいただいていました。
任期が2年過ぎ、色々なことも分かってきたタイミングで、コロナ禍になってしまい、後半2年間は教育委員としての活動が限られてしまいました。思うように活動ができない中、高額のお給料をもらっているのにこのままでいいのか、教育委員の任期は4年ですが、その後も川崎市や社会に役に立たなければと思うようになりました。
地域活動も色々とさせていただいて、教育委員として川崎市の教育を広く考える経験も与えていただき、やはり次は政治の世界をやったほうがいいのかなと。また、女性議員もなかなか増えないし、誰かがやってくれるのを待つのではなく、自分が政治の世界に飛び込むべきではないかと考えました。
また、ちょうどタイミングもよくて、教育委員の任期が切れてから1年後に、統一地方選。お金も何とか用意できる。夫はコロナ禍以来、在宅勤務。親は元気で介護はない。子どもも手が離れた…と、選挙に出られる条件がそろっていました。これは、選挙に出なさいと言われているんだと思いました。

「子育て支援」を掲げて選挙に臨んだ
■肩身の狭い思いで子育てをする土壌がおかしい
―公約に子育て支援を筆頭に掲げていますが、日本ではまだまだ子育てに関して厳しい現実があるのでしょうか
高橋:私は、末っ子が中学生になり、子育てはひと段落しています。でも、子育てをしている最中では、とにかく周りに迷惑をかけないということを一番に考えて行動していました。いつも謝りながら、子どもを連れ歩いていました。しかし、それはおかしいですよね。
ある時、川崎駅前のアゼリアで大泣きしているお子さんをだっこしながら困っているお母さんがいました。声をかけて、ベビーカーをトイレまで押してあげました。トイレに行きながら、お母さんが号泣して「すいません」と言うんです。自分にも同じような経験があるので、「全然、すいませんじゃないですよ」と声をかけました。
子育ては未来の社会を支える人材を育てることでもあります。どうして、こんなに申し訳ない気持ちになりながら子育てしなければならないのか、おかしいと思います。私は、子どもは社会全体で育てるものだと思っていますから。
■放課後、子どもを見守る大人の目が激減している
―地域で子どもを見守る仕組みを作るという公約があります
高橋:放課後に子どもだけしかいない公園が増えていて、子どもを見守る大人の目がどんどん減っていると感じています。例えば、自分の住まいの近くの公園では、放課後に、小さな子どもに付き添っている保護者さんの姿をほとんど見なくなりました。すべての子どもを見ていなくても、子どもの遊んでいる場所に、なんとなく大人がいて、子どもが困ったら大人に助けを求めるというのが難しくなっているのかなと思います。
防犯という意味でも、大人の存在は重要です。
子育てをしている保護者の方たちに時間的な余裕がどんどんなくなっているとはいえ、どうやって当事者たちでもリソースを出して、子どもたちを見守れるか、また子育て当事者以外の人たちをどうやって巻き込めるかを考えています。具体策はなかなか浮かばないのですが、ますます重要になる問題だと思います。
―高齢者の方に見守り役をお願いできませんか
高橋:高齢の方でも働いている方が増えていますし、地域活動に関心の薄い高齢者の方も増えています。地域のために動ける方が減っているというのが、実感です。公園の見守りをお願いする、というより、散歩のついでとか、買い物のついでとか、負担にならない形で、子どもに目を配っていただけるといいですね。

「公約」をどう具体的に市政に反映させるか
■単身者が地域とつながる仕組みを模索
―一方、幅広い世代が参加する持続可能なコミュニティの構築とは
高橋:今、様々な地域コミュニティが行き詰っている要因の一つは、世代交代がうまくいっていないことだと思います。世代交代がスムーズにできないと持続できません。世代交代を進めるためには、時代に合った仕組みに変わっていくことが必要です。なかなか難しいですが。
また、今後は単身者がどんどん増えていきます。子どもがいると、地域とのつながりは自然に増えますが、一人暮らしですと、自分から意識的に動かないと、なかなかつながりは増えません。地域のつながりを煩わしい、不要だと考える方もいらっしゃいますが、何か困ったことがあったときに助けてもらうためには、やはり地域(周囲)とのつながりが重要になります。
例えば、多摩川の氾濫のような災害時やコロナにかかった時のような非常時に、単身者で近所にまったく頼る人がいなければ、命にかかわる状況に陥ってしまいます。その辺りも意識して、色々な人が気軽につながることができるコミュニティを作っていきたいと考えています。
もちろん、同好会や、勉強会のような地域とは違ったコミュニティもありますが、そういうコミュニティは、積極的に参加する人しかつなげられない。積極的に参加しない人でもつながってもいいなと思えるような仕組みづくりも意識しなければいけないと思います。
今の時代、SNSなどネット上でつながる人も増えていますが、そこからもこぼれてしまう人にどう手を差し伸べるかも課題です。
―民生委員制度の活性化はいかがでしょうか
高橋:私は、民生委員の有償化を進めていきたいですね。今までの福祉というのは、民生委員という無償ボランティアの方々がいるという前提で、いろんな仕組みが成り立っていました。でも、私たち世代は老後も年金がどのくらいもらえるのか分からない、かなり高齢まで働く必要があるかもしない。現在の民生委員のお仕事を無償で引き受ける余裕はなさそうです。
民生委員の充足率が低下している現状を見ても、無償ボランティアで成り立っていた今までの制度は、破綻しかかっていると思います。だから、私は有償ボランティア制度に移行していく必要があると思っています。
■元気な街だからこそ地域コミュニティとつながれる街にしたい
―中原区をどういう街にしたいですか
高橋:やはり若い世代が多いし、お子さんも多い。少子高齢化が進む日本の中でも、元気があって将来性もあるすごく稀有な街だと思っています。その元気さをまずは失わせない、ということが一番大事かなと思っています。
さらに、多様な世代が混ざって地域のコミュニティとつながれる街にしたいです。災害など困ったことがあったときに、助け合える街にしたい。元気で余裕がある街だからこそできることだと思っています。余裕がなくなると、つながることも難しくなるので。
―キャッチフレーズが「市政とつなぐ、みんなをつなぐ」ですね
高橋:私の周囲でも、市政とつながっている人は少ないように感じています。市政は自分たちの生活の基盤になるものなので、市政とつながっていると皆さんに感じていただきたいし、そのためには色々なことをわかりやすく伝えていきたいと思います。
また、みんなをつなぐというのは、市民同士をつなぐという意味も含んでいます。地域の人たちが様々なつながりを持って、助けあえる社会にしたいです。
高橋みさとホームページ:https://takahashimisato.com/
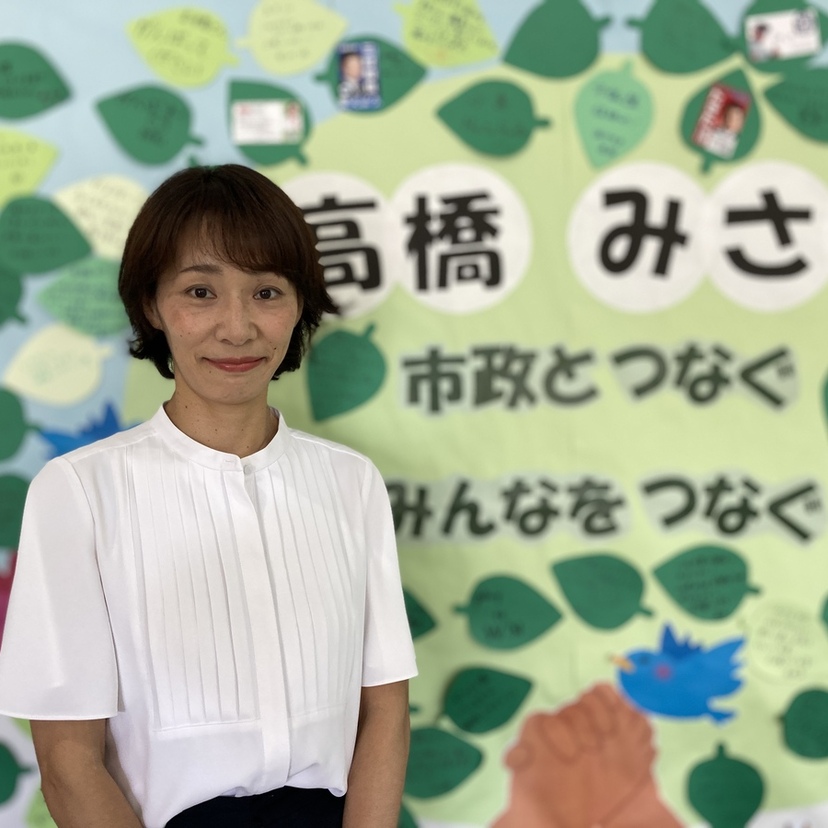
















現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。