■食と映像作品が融合したフードエンターテインメントを志す
―大学を卒業してテレビ局系の会社に就職されましたね
奥村:学生の頃から映画監督になるのが夢だったので、映像にかかわる仕事がしたくて、日本テレビのグループ会社に入社し、パッケージプロデューサーをしていました。ドラマを中心に担当していたので、撮影現場に行き、特典映像を作ったり、字幕を付けたり、音楽などの権利処理などをやり、パッケージデザインもデザイナーさんと作って、DVDBOXなどのパッケージにする仕事を7年間やっていました。
―そこから一転、カレー専門店を始める経緯は
奥村:商売という意味では興味がなかったので、お店をやりたいという気持ちではなかったのですが、大学生活の4年間、飲食店でアルバイトをしていたのがすごく楽しかったことと、料理がとても好きで調理師免許もとっていたのもあったのと、私がやっていた映像の仕事は、誰かが作ったコンテンツをパッケージングにする作業だったので、「やっぱり自分で創作・表現をしたい!」という気持ちがくすぶっていたのが、ある時結びついて!
そこで、コース料理と映像作品が融合したようなもの、例えば1時間の映像作品を作り、作品の中で出てきた料理が鑑賞中に順番にでてくるとか、そういう食事体験をエンターテインメントにするような仕事ができないかと考えました。
そういった食と映像を融合させたフードエンターテインメントができれば、自分も作品を作ることができるし、飲食も手掛けられるので、これはもう自分で会社を作るしかないなと思ったのです。夫は同じ会社の先輩社員だったのですが、彼も独立したいという気持ちがずっとあって、それでは一緒にやろうかということで、二人で2009年に株式会社サウンドキッチンを設立しました。
■開店当初は三輪車を引いてまち中でカレーを売り歩く
ですから、ただ商売としてお店をやるわけではなく、つねにエンタメ性を持たせることを大事にしています。なぜカレー専門店かと言えば、それは単純に私がカレーが好きで学生の頃から食べ歩いたりもしていたからです。お店のオープンは2011年です。開店当初は、同じ場所で音楽教室を並行して開いていたので、その音楽教室がある時間は、自分が街に出ていこうと思い、三輪車を引いてまち中でカレーを販売していました。
また、エンタメ業界にいたこともあり、情報発信が得意だったので、“対話式カレー屋”と称して、お客さんと常にツイッター(X)などのSNSで、「今度、どんなカレーを食べたいですか?」などと投げかけて「それじゃ、中華風カレーを作ってみて」などお客さんと対話をしながらメニューを開発していました。

開店当初は三輪車を引いてまち中でカレーを販売していた
―100種類に到達するまで毎週必ず新作カレーを作ったそうですね
奥村:対話式カレーをしていると色々なご意見をいただけるので、それに応える形で今度は目標を立てて、50種類到達、100種類到達を目指すのをお客さんも応援してくれました。目標は2、3年で到達して100種類到達したときには、記念パーティを開催して、これまで開発した100種類のカレーの写真を壁一面に貼りだして、お客さんに投票してもらい、上位3種類の食べ放題パーティーをやりました。
とはいえ看板メニューは「濃すぎチキンカレー」で、やはり看板になるメニューは開店時から店に出そうと自分がずっと開発してきたものです。また「和ジアンカレー」も開店前から開発していました。

看板メニューの「濃すぎチキンカレー」は絶品!
■一大イベントに成長した「武蔵小杉カレーフェスティバル」
―お店をやられていて苦労したことはなんですか
奥村:苦労したのは単純に資金繰りが大変だったことですね。開店してから、3~5年目ぐらいが一番辛かったですね。今も自転車操業に変わりはありませんが、当時、なんとか続けていくために、保険をどんどん解約したり、借りられるところからはすべて借りたり、夫の退職金も1年で使い果たしたりとなかなか壮絶でした(笑)。やめるお金もないよねといった状況でしたね。
―ところで地域とのつながりも活発ですね
奥村:移動販売でまち中を練り歩くようになったら、今まで全然目を向けてなかった、まちの人たちと交わるようになりました。また、同じまちで商売をするお店と関わるようになりました。そうしたら、みなさん、面白いんです。お客さんの中にもすごく面白い活動をしている人がいたり。それこそまちを盛り上げるために色々なことをやっている人たちとつながっていったんですね。
そうするうちに、私もまちを盛り上げたいなと思ったり、地域の方たちとコラボしたり、商店街のみなさんで集まって、たとえばスタンプラリーなんかを企画してみたいなと思うようになりました。ただ、そういう企画を立てだした時期は、実はお店としてはとても苦しい時だったので、私が企画に足をとられて店を空けることによって、お店には迷惑を掛けましたね。
―武蔵小杉カレーフェスティバルは大きなイベントになりました
奥村:2015年に私が発起人になって「武蔵小杉カレーフェスティバル」を立ち上げたのですが、当時、「コスギフェスタ」という地域最大のイベントがあって、2013年にその「コスギフェスタ」に出店者として参加することから始まったのです。翌年には運営者側に回ることになり、2015年にはカレーフェスティバルをしたいんですというプレゼンをしたら、みなさん賛同してくださり、「コスギフェスタ」の前夜祭としてスタートしたのです。
それまでフードフェスというのが武蔵小杉にはなかったので、ものすごく盛り上がって、これは毎年やるべきだね!とみなさんが動いてくれて、コロナ禍の間を除いて、毎年開催しています、ちなみに2018年にはコスギフェスタと合わせて3万人近くの方に来ていただけました。自分としては大きな成果でしたね。

今や大イベントに発展した武蔵小杉カレーフェスティバル
■食べログの「カレー百名店」に選ばれ川崎市ではNo.1に
―ちなみに「新丸子ゴールデンルートクラブ」を結成されたとか
奥村:私が仲良しなお店に声をかけて、みんなでコラボして新丸子を盛り上げよう!といったことをしていました。新丸子には商店街が4つあるのですが、どこの商店街に属しているかというのもとっぱらって、それこそ商店街に属していなくても、同じ新丸子というまちでお店をやっているということだけでつながって、街を盛り上げたいなという気持ちのある店が集まって色んな企画をやっていくという感じです。現在は「新丸子路地裏連合」として、写真道場さんが音頭をとってくれています。
それぞれのお店には常連さんという名のファンがいるので、その常連さん同士をつないだら面白いのではないかという発想から、「新丸子のガイドブックをお店とお客さんで一緒になって作ろう」という企画を立てたのです。
お客さんにお店の人や店やまちの風景を撮ってもらい、ガイドブック内のイラストも文章も私たち店主が創って、自分で「新丸子で1日を過ごす」という設定にして、担当のお店を4つ盛り込んで、こんな1日を過ごしたよという物語をみんなで書きました。それぞれの人が、新丸子のどんな「ゴールデンルート」で1日を過ごしたかをガイドブックに仕上げました。
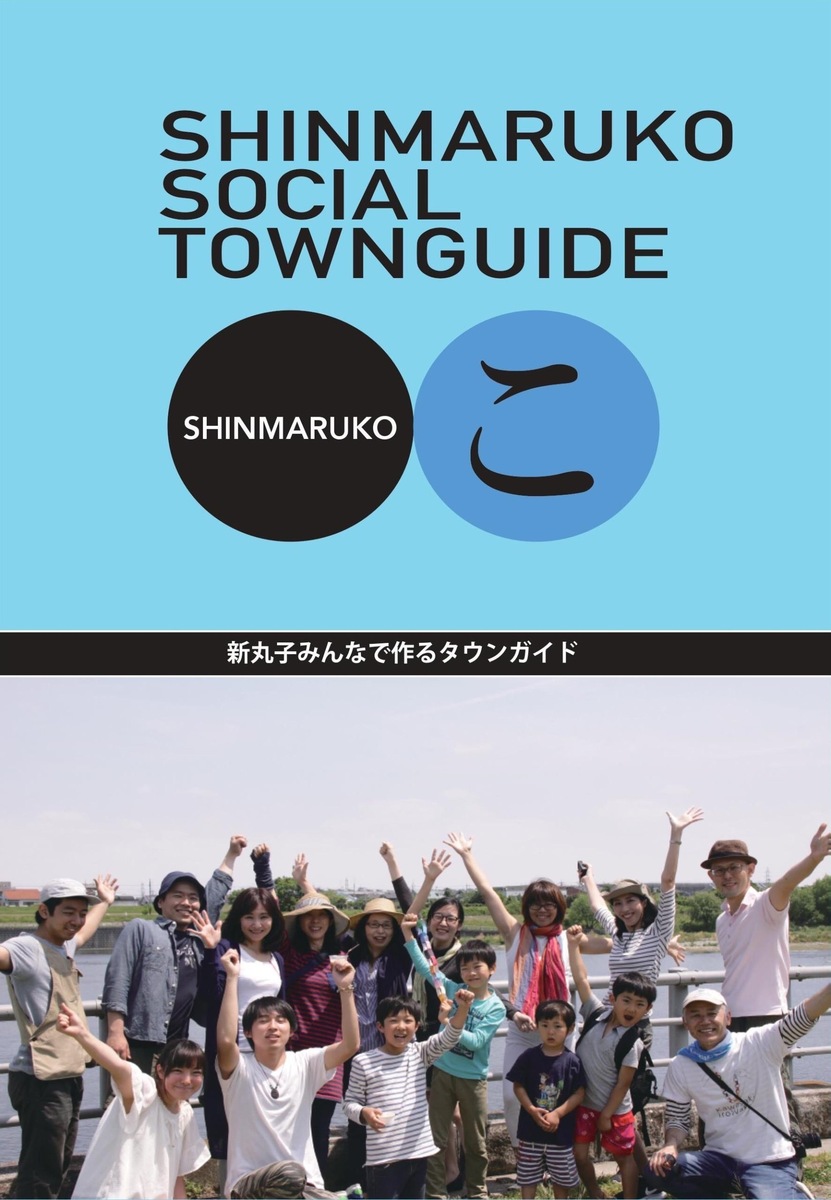
お店の常連さんたちと創り上げた新丸子のガイドブック
―肩書として料理研究家と作家というものもありますね
奥村:ここ数年はカレー屋さんを1年で200店舗以上、食べ歩いています。1日で2~3軒お店を回ったりすることもあり、色んなカレーを食べるのが一番勉強になるなと思いログを残していました。だけど、やっぱり私は根底に表現をしたい、作品を創作したいというのがあるので、常に詩を書いたり小説を書いたりを続けていて。直近ではカレーの食べ歩きの記録をフィクションに仕立て、同時に撮り溜めていたカレーの写真や店内・風景のスナップと一緒に小説作品にしました。
―今後の抱負を教えてください
奥村:お店は14年目なのですが、開店当時は映像業界からいきなり転身してきたというのもあり、色物のように見られるのが仕方ないながらもとても嫌でした。ただ、私は修行こそしていたわけではありませんが、料理はずっとやっていて調理師免許までとっていたし、カレーに関しては相当食べ歩いていたという自負もあったので、ちゃんと飲食店としても認めてもらいたいという気持ちでやってきました。
そうしていくうちに、2019年に食べログの「カレー百名店」に当店が入ったのです。今でも「川崎市 カレー」で検索すると、当店が1位です。さらに「神奈川県 カレー」で検索すると3~4位です。色々な活動はしていますが、カレーそのものを評価していただける努力は惜しみませんでした。
一つの指標にすぎないものですが、百名店に入ることで、やはりお客さんも増えたので、もう少し風格のあるお店になりたいと思っています。また、14年経った今でも「こんなお店あったんですね!いつできたんですか?」と言われることも珍しくはなく、もう少し知名度をあげなくてはと思ってます。
また、「武蔵小杉カレーフェスティバル」に関しては、10年前の私のように、「やりたい!」と手を挙げる人を応援したいと思っています。そういう若い人と巡り会って、「武蔵小杉カレーフェスティバル」を若い人たちと育てたいし、その人たちがメインとなって動いて、私が応援するといった形になれば理想的だと思っています。
一生続けていきたいのは、自分の創作だったり、もともとお店を立ち上げたときのアイディア…映像作品と料理が連動しているようなものを実現させたいですね。そういう体験型コース料理を、映像で表現したい人・料理で表現したい人がチームとして集まって創ってみたいですね。
―読者へのメッセージをお願いします
奥村:武蔵小杉が「このまちでなにかやりたい!」という若い人たちがその夢を実現できるまちであったらなと思っています。色々な夢はあると思いますが、自分が暮らしているまちで自己実現したい人がいたら、このまちにはすごく応援してくれる人がたくさんいます。
私が「武蔵小杉カレーフェスティバル」を立ち上げた時のように、思っているだけではなく、一歩踏み出したら、色んな人が協力してくれるということを自分で体験したので、読者の方の中で、武蔵小杉で何かやりたいと思っている人がいれば、声に出してくれれば、協力してくれる人はたくさんいるよということを伝えたいです!


















現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。